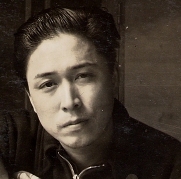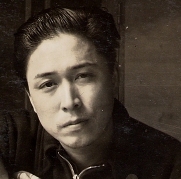父の情景
2002年7月27日未明、父が亡くなりました。7月7日の突然の入院から20日目でした。77歳。意識を取り戻すことはありませんでした。通夜、告別式とあわただしく過ぎていきながら、想いはいつも父に還っていきます。
私が生活を別にしてから、父とはめったに逢いませんでした。その間、父が「父」であることに安心しきっていました。まるで、今がいつまでも続くかのように。
情けないことに、父を失ってはじめて父を本当に理解してきたような気がしています。父の優しさも、父の孤独も、父の生き様も・・・。人間としての父を今ほど身近に感じたことはありません。生きているときにもっともっと交わす言葉があったはず、自責の念が心を離れません。
父への思いを少しでも、文字にしてみようと思いたっています。父がどこかでこれを読んでいてくれることを祈るような気持ちで。父の息づかいを感じたいと思いつつ・・・・。
1 2002.8.11.
「世の中は間違っている」 いきがって言う私に
「おまえ 世の中は そんなに甘くない」 と父
その「言葉」にこだわった私
中学生の生意気盛りの頃の話
それっきり忘れられたその会話
父から独立して 私は一人で暮らすようになった
そして40年近くが過ぎた
私は いつしか「世の中」にどっぷりつかっていた
「おまえは 正義感が強いから・・・・」
ある時ぽつりと父の口から出た
私はどきりとした
あのときの私を 父は受け止めていたんだ!
ずっと ずっと受け止めたまま生きてきたんだ
一人歩きをはじめた私の危なっかしいあゆみに
父は二度と口を挟もうとしなかった
受け止めなかったのは私だ
成長してなお 父の思いの深さを悟らなかったのは 私の方なんだ
なぜ もっと話をしなかったのか
なぜ 「父」と「子」でなく 人間として向き合わなかったのか
なぜ 父の遠慮がわからなかったか わかろうとしなかったのか
痛みが走る
大人になってから 父と争った記憶がない
それがどういうことだっのか 長い間考えてみようともしなかった
我慢していたのは 断じて私ではない
耐えていたのは 父だったのだ
一人前に扱うことの代償に
父は 言葉を失った
寂しさを受け取った
もどかしかったことだろう
母がぽつりと言った
「おとうさんは とうとう 孫の顔を見ることもなかったね」
結婚というものに縁の無かった私は 返す言葉がない
諦めを自分に課した父
悔いが 私の全身を駆けめぐる
2 2002.8.13.
七夕に発病し
病院のベッドで 眠り続ける父
祭壇のように並んだ
人工呼吸の機械 点滴のスタンド 心電図のパネル 透析機・・・
私たちは 祈るような気持ちでその祭壇にぬかずく
父の体は熱く
むき出しになった足は白く、私の皮膚よりもつやつやとしている
その足の裏をくすぐる母を 誰も笑えない
「そろそろリハビリのことを考えましょう」
「歯ブラシも持ってきておいてください」
医師の言葉が希望の灯をともす
容態が急変した
心筋梗塞にめげずに
命を永らえるさせようと動き続けた心臓の
足取りが重くなった
3人の医者が心臓マッサージを続けた60分
・・・・・・帰ってこなかった・・・・・・・・
そんなはずはない
父の意識はもどっていた
動けなくなった体を感じて
プライドの高い父は
自分で生きることをやめたんだ そうつぶやいた妹
おまえの悔しさが お兄ちゃんにもよくわかる
お別れに来た従兄弟が言った
「おじさんは 7月7日に亡くなったんだ
そのあと20日間は
お前たちに覚悟させるためにおじさんは生きてくれたんだ」
私は 父が 船に乗り損ねたような気がした
七夕の彦星は 天の川の向こう岸から
とうとう帰らなかった
あちらに 織り姫は 父のためにいてくれただろうか
3 2002.10.11.
幼い日の 夕食の情景
食卓に並んだ シューマイ
夜遅く帰ってくる父の
ささやかなお土産
それが楽しみだった
シューマイのおいしさと
シューマイのかすかな湯気の絵が
心の片隅に残った
ある日 横浜の駅に降り立ったとき
懐かしいシューマイを見つけた
ためらうことなく買い求め
胸に抱えて家路を急いだ
食卓に並んだ シューマイは
しかし とりたてて おいしくはなかった
ただのシューマイの味だった
あの幼い日の食卓の
シューマイのおいしさは
いったい 何だったのだろう
残りのシューマイを
急いでお茶と一緒に飲み込んだ

4 2002.12.4.
駅からタクシーに乗りながら考えている
前から気になっていた
父の退職後 ずっと続けていた仕送り
打ち切りになったのは
僕自分のローンが始まったときだ
やはりローンを払い続けていた父が
もう仕送りはいいぞと言い出した
ほんとうに大丈夫なのか?
それまでたまにあった生活費の不安が
父の口から聞かれなくなった
父の葬儀が済んで
父のローンがまだ残っていたことを知った
年金生活で楽だったはずはない
なぜ父は 仕送りの停止を言い出したのか
前の席で運転していたドライバーが
いつの間にか 父になっていた
「それは プライドだよ。」と一言
もとのドライバーに戻って
タクシーは
闇の中をしずかにすべっている
納得する
僕がローンをはじめたとき
自らローンをかかえていた 父は心配したのだ
「それはプライドだよ。」
ああこれは優しさの形だったのだ
制作 さすらい人 2001〜