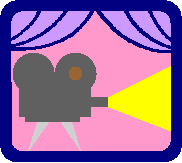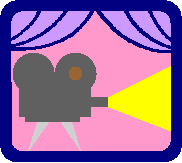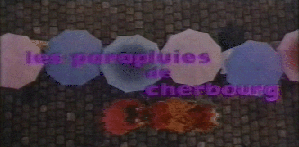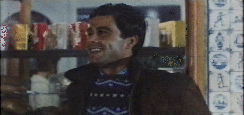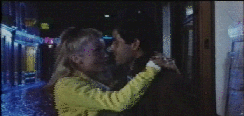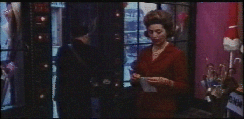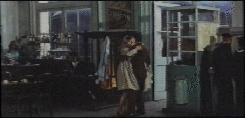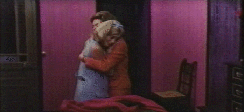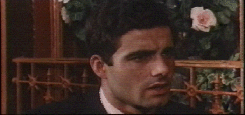制作 さすらい人
映画の棚
キャスト 【配役】 【歌唱】
ジュヌヴィエーヴ カトリーヌ・ドヌーヴ ダニエル・リカーリ
ギー ニーノ・カステルヌオーヴォ ジョゼ・バステル
エムリー夫人(母親) アンヌ・ヴェルノン クリスチャンヌ・ルグラン
ローラン・カサール(宝石商) マルク・ミシェル ジョルジュ・グラネス
マドレーヌ エレン・ファルネ クローディーヌ・ムーニェ
伯母エリーズ ミレイユ・ペレエ クレール・ルクレルク
1964年 フランス・西ドイツ(当時)合作作品 91分
ビデオ Victor CBS/SONYOOZF 3002
DVD ヘラルド発売 ソニー販売 SHD−10533
主な登場人物
シェルブールの雨傘
1964年 カンヌ映画祭グランプリ
ルイ・デリュック賞
フランス映画高等技術委員会賞
国際カトリック映画事務局賞
原案・シナリオ・作詞・監督 ジャック・ドゥミ
音楽 ミシェル・ルグラン
撮影 ジャン・ラビエ
Les Parapluies de Cherbourg
高校生の頃見た映画。全編歌になったミュージカルと聞いて、音楽好きの私は、一も二もなくとびついたものだった。が、ただそれだけの映画ではなかった。
ミュージカルといっても半端ではない。せりふすべてが歌になっている。郵便屋さんの「郵便。」のかけ声から、通行人が道を尋ねる一言までが歌なのである。それでいて、中に出てくる人たちの演技は、ふつうの映画のようにごく自然に流れていく。音を消して見ていたら、ミュージカルとはわからないだろうと思う。また、突然踊り出したり、せりふが途中から歌になったりといったことはおこらない。映画の形をしたショーではなく、完全に物語を主体とした映画なのである。
映画を見るに当たって、いくつか知っているとわかりやすいかもしれない。
この映画の中の時間は、1957年11月から1963年のクリスマスまでの6年間である。ギーとジェヌビエーブの人生を変えてしまうことになるギーの出征の背景にあるアルジェリアでの戦いとは、1954年から7年半にわたって戦われたアルジェリアの独立戦争のことである。アルジェリアは1962年にフランスの植民地支配を脱し、共和国となる。
舞台になるシェルブールは、フランス北部の英仏海峡に面した港町である。(映画の冒頭に出てくる左の画像参照) 物語の始まったとき、ギーは20歳、ジェヌヴィエーヴ16歳という設定。従って、物語の終わりでも、二人は、26歳と22歳ということになる。若い二人なのである。ついでに言うと、監督のドゥミと音楽のルグランは、ともに1931年生まれなので、この映画を制作したとき30歳代の前半である。
物語
1957年11月 第1部 旅立ち
傘屋の娘ジェヌヴィエーヴとガレージで働くギーは恋人同士。仕事の終わったあと、劇場に行ったりダンスに行ったりデートを楽しみ、「子どもが生まれたら、フランソワーズという名前にしましょう。」「傘屋をしましょう。」「ガソリンスタンドをやろう。」などと話し合いながら将来を夢見ている。
ギーは、アパートで伯母さんと一緒に暮らしている。体の悪い伯母さんの世話をマドレーヌがしている。

ギーとの交際を知った母親は、「若すぎる。兵役だってすんでいない。」と反対する。

娘と口論したあと、母親は税金の督促状を受け取る。経営の苦しい傘屋は破産の危機に瀕している。思いあまった母親は、手持ちの宝石類を売るために娘と宝石店に出かけていく。たまたま居合わせた宝石商のカサールが、買い取ってくれることになる。

母親にギーとの交際を反対されたことをギーに訴えようとしたジェヌヴィエーヴはに、暗い顔をしたギーは、2年間の兵役のための召集令状がきたことを伝える。
「2年間は私たちの人生にとっては長すぎるわ。」
「私が守ってあげる。私が隠してあげる。だからね行かないで。」
「あなたがいなかったら生きていけない。」とジェヌヴィエーヴ。
「僕が帰るまで待っててくれるね 。」
「残り少ない時間を大事につかおう。」
二人の切々たるやりとりの場面が続く。
ギーはジェヌヴィエーヴを自分の部屋に誘って、そこで最後の時間を過ごす。

宝石の代金を持ってカサールがジェヌヴィエーヴの店を訪れる。カサールさんがくるからとひきとめる母親を振りきって、ギーにあうために出かけていってしまう。入れ違いにカサールが訪れる。
ギーの出征を悲しむジェヌヴィエーヴを気遣う母親。
出発の朝、病身の伯母をマドレーヌに託してギーは出かけていく。外では、ジェヌヴィエーヴが待っている。
駅での別れ。この映画で最も有名な場面。テーマ音楽が哀切に響き、ギーの「モーナムール」とジェヌヴィエーヴの「ジュ・テーム、ジュ・テーム」の歌がいつまでも胸をかきむしる。91分の映画のうち、ここまでで約41分。このあと、ラストの1963年のクリスマスでの偶然の邂逅まで、二人は顔を合わすことはない。2度目以降筋がわかっていてこの場面を見ていると、切なさが、ひとしおである。
1958年1月 第2部 不在
1958年2月。
ギーからの手紙が届く。
「君はぼくの誇りだ。フランソワ、いい名前だね。」
「いつかえれるかわからない。君は待っていてくれるね。」
ギーの写真を見ながら、カサールからきた手紙に返事を書くジェヌヴィエーヴ。なかなか筆が進まない。
1958年4月カサールから指輪が贈られてくる。母親は、将来のわからないギーでなくカサールとの結婚を願っている。やがてシェルブールに戻ってきたカサールは、ジェヌヴィエーヴに、結婚をして、子どもは自分たちの子どもとして育てようと言う。
カサールと結婚したジェヌヴィエーヴは、そのままパリへとたつ。
1958年3月。おなかが目立ってきたジェヌヴィエーヴ。ギーの手紙が届かない。「いない人って不思議ね。出かけたのはずいぶん昔のような気がする。写真を見ないと顔まで忘れてしまいそう。もし、このおなかを見ても気持ちが変わらなかったら、カサールの誠意は本当だし。だから悩むの。いないっていうのはなんて辛いことなの。私はどうして死んでしまわなかったのかしら。」と嘆く。
1959年3月 第3部 帰還
1959年4月。昔の勤め先に戻ったギー。しかし、すさんでいて、雇い主とけんかをしてとうとう勤め先を飛び出してしまう。あてもなく、町をさまようギーの足は、自然にジェヌヴィエーヴのいた雨傘店に向かう。しかし、そこは新しい店への改装工事が進んでいた。そのまま酒場へ行き酒をがぶ飲みする。声をかけてきた娼婦のところに泊まり込む。余談だが、この映画に出てくる人はみなやさしい。娼婦もまた、「ジェヌヴィエーヴと呼んでもいいのよ。」とギーに声をかける。
一晩戻らない間に、伯母が亡くなっている。伯母の葬儀を済ませたあと、出ていこうとするマドレーヌに、残ってくれとギーは懇願する。すさんだ今のギーは嫌いだとためらうマドレーヌだったが、最後に承知する。
1959年6月。伯母の残した遺産を整理したギーは、ガソリンスタンドを買い取り、新しい出発をしようとする。
すべての手続きを終えたギーは、待っていたマドレーヌのところに行くと、結婚を申し込む。
(ひそかにギーに思いを寄せていたらしい)マドレーヌは、返事をためらう。
「こわいの。あなたがジェヌヴィエーヴのことをまだ想っているのではないかと思うと。」
ギーは、ジェヌヴィエーヴのことはもう忘れたときっぱりと言う。
1963年12月クリスマス。4年半の月日がたっている。すっかり立ちなおったギーは、ガソリンスタンドを経営しながら、マドレーヌとフランソワという男の子と3人で幸福に暮らしている。雪の降りしきるクリスマス・イブ。子どもを連れてマドレーヌは買い物に出かける。入れ違いに入ってきた1台の車。給油のために近づいていったギー、車のジェヌヴィエーヴ。シェルブール駅以来の邂逅だった。はっとなってお互いを見つめる二人の目と目。
体調を心配する母親に、ジェヌヴィエーヴfは妊娠していることを告げる。
その日宝石商カサールを食事に招待していた母親は、思い悩む。
食事のあと、気分が悪いジェヌヴィエーヴが座をはずすと、カサールは母親に、ジェヌヴィエーヴへの思いをうち明ける。3ヶ月後に返事を聞かせてほしいと言い置いて、カサールは立ち去る。
ギーが戻ってくる。戦争で負傷した足を引きずりながら、まっすぐ、ジェヌヴィエーヴの雨傘店に向かっていく。が、懐かしい店はなくなっていた。ウインドウには、「持ち主が変わりました」と貼り紙がされている。
アパートに戻ると伯母は体がすっかり弱って寝ている。カサールと結婚したジェヌヴィエーヴのことを教えてくれる。
「おまえ気がつかなかったのかい。」
「そういえば、最後の頃の手紙は投げやりになっていて怒っているのかと思っていた。病院に入るとその手紙もこなくなった。」
伯母と世話をするマドレーヌとここだけは変わっていなかった。
「寒いわ。」「事務所においで。」ふたりの最初の会話。
表情の硬いジェヌヴィエーヴと平静に振るまうギー。何となくぎこちない。
とりとめのないような会話がぽつんぽつんと続く。
「義母のところに預けていた子どもを迎えに行ったの。」
「シェルブールは結婚以来初めてだわ。」
「黒い服だね。」「母が亡くなったの。」
車の中に女の子がいる。
「あんたにそっくりだわ。」
「名前は?」「フランソワーズ」
「会う?」 しかし、ギーは静かに首を横に振る。
そして、「君はもう行った方がいいよ。」
黙って出て行きかけたジェヌヴィエーヴは、振り返って言う。
「あんた、元気?」 「ああ、とっても元気だよ。」
これが二人の最後の会話である。ジェヌヴィエーヴは車に乗ると黙って去っていく。
まもなく、買い物から戻ったマドレーヌと男の子フランソワの方に、ギーは笑顔で駆け寄っていく。そして、子どもとふざけ合うのである。
ふりしきる雪の中で映画は終わる。
この映画を最初に見た高校生の時、無性に腹が立ったのを覚えている。好き合った二人がなぜ結ばれないのか、そんな思いだった。今改めて見なおしてみて自分も年をとったかなあという気もする。腹は立たない。控えめなマドレーヌがギーと幸せになった、よかったなあと思う。昔いやなやつと思ったジェヌヴィエーヴの母親の気持ちもわかる。途中から出てきてジェヌヴィエーヴと結婚したカサールが立派な紳士であることもわかる。当時、ギーとジェヌヴィエーヴの手紙が続かなくなったのは、もしかして母親が隠したのではと邪推したのは間違いだったこともわかる。けれど、幸せな家族の景色の中で終わるラストシーンのあとも、悲しみが残るのだ。なぜだかわからない切なさと痛みが残る。
最後に出会った二人は、とりとめのない会話しか交わさない。思い出も語らないし、相手につっこんだりもしない。淡々としているように見える。しかし、二人の表情からは、それ以上のものが伝わってくる。また、ふたりとも子どもにフランソワ、フランソワーズと名前をつけていることも気づかないわけにはいかない。二人はどんな思いを抱えてこれからの人生を生きていくのだろう。
日付を追っていって、ひとつ気になることはある。ギーが出征したあと半年ほどでジェヌヴィエーヴはカサールを受け入れている。こんなにはやく心変わりがするのだろうか、この辺が私にはわからない。その思いがあればこそ、ラストのあとの悲しさがどこかに割り切れなさとしてひっかかったまま残ってしまう。あの駅での別れの想いの深さに対して、気持ちの変容が早すぎる。ギーと分かれるとき「あなたがいなければ生きていけない。」と言っていたジェヌヴィエーヴが、カサールの求愛の中で「なぜ私は死ななかったのかしら。」という。あれはジェヌヴィエーヴの自分自身への問いかけだったのかもしれない。ジェヌヴィエーヴがもっと年がいっていたら、あるいは違った結論を出したかもしれないなと思う。ギーがもっと年輩だったら、あるいは立ち直れなかったかもしれないなあとも思う。こんなことを考える私自身は若くないのかなあ。
もうひとつ。背景にあるアルジェリア独立戦争がなかったらふたりの恋は成就したかもしれない。「シベールの日曜日」の背景には、第1次インドシナ戦争があった。(いずれもフランスからの独立戦争だ。)「エル・スール」の背景にはスペイン戦争があった。映画で直接戦争のことを訴えているわけではないけど、戦争がもたらす悲劇におもいがいってしまう。現に世界のあちこちから戦争がなくなっていない以上、今もたくさんの悲劇が生まれているのでは。結ばれない二人が生まれているのでは・・・とりとめもなくそんなことを考えてしまう。
単純なストーリーながら、味わいの深い作品である。音楽のすばらしさと一緒に、若いカトリーヌ・ドヌーヴの初々しさも忘れられない。ドヌーヴに会ってみたくなる。シェルブール雨傘店の客になってジェヌヴィエーヴのドヌーヴに・・・・・・・・・・・・・
つれづれに
追記
二人の結婚の意味は何だったのだろうと考えてみた。ジェヌヴィエーヴとギーの恋からは燃えるような想いが伝わってくる。その激しさは、「あなたなしでは生きられないわ。」というジェヌヴィエーヴの言葉に象徴されている。
カサールと結婚するときのジェヌヴィエーヴは、おなかに子どもを抱えたまま、戦地に行ったギーとの連絡がとぎれがちで一人取り残された不安のまっただ中にいた。そこに「僕たちの子どもとして育てよう。」とカサールの手がさしのべられた。一方のギー。戦地から懐かしいシェルブールに戻ってきたが、そこにはジェヌヴィエーヴの姿はなく、二人が笑顔をかわしあった傘屋のウインドウも消えている。現実の町を当てもなくさまよい歩くギーの心の中は過去のままだ。ただひとつ昔のままだった伯母は亡くなり過去の足場のもう一方も消えてしまう。そこに、変わらぬマドレーヌがいた。ジェヌヴィエーヴとカサールの結婚も、ギーとマドレーヌの結婚も、かってのジェヌヴィエーヴとギーのような激しく燃える恋情はない。が、そこには、翼を休めることのできる平穏がある。安らぎを求めての結婚、そんな気がする。ラストでの二人の肝心なことは何も語らない会話は、そのことをお互いに了解しているからだろう。例え、痛みが残っていたとしても・・・。遺憾ながら(かな?)、素直に心と心を寄せ合った20歳と16歳の時の二人から少し大人になってしまっていたのだろう。語られない心のひだの奥の悲しみがラストシーンの哀切感になるのかもしれない。
もうひとつ感じたことがある。生まれる前に、手紙の中であれほど楽しみにしていたジェヌヴィエーヴとギーの子どもフランソワーズ(女の子)。最後のシーンのガソリンスタンドの中で、ジェヌヴィエーヴが「あなたにとてもよくにている。」「会う?」と言ったとき、ギーは静かに首を振る。ギーは、昔の懐かしい思い出につながる対面をさけたのだろう。が、心の中は複雑だったに違いない。「君はもう行った方がいい。」とすぐに答えるギーの言葉がそれを裏付けているようにみえる。ジェヌヴィエーヴが去り、マドレーヌと男の子フランソワが戻ってきたとき、走り寄ったギーが男の子を抱え上げ、一緒にふざけまわるシーンは、楽しそうに見えるがとても辛い。そのときギーの心は、二人の子フランソワとフランソワーズを抱え上げていたに違いないと思うから。そのギーの姿をいたわるようにカメラは後ろに引き、ギーとジェヌヴィエーヴの懐かしい過去を彼方に押しやったように、この物語をも遠くに押しやり静かに終了する。降りしきる雪がすべてをつつんでいく・・・・・・・。